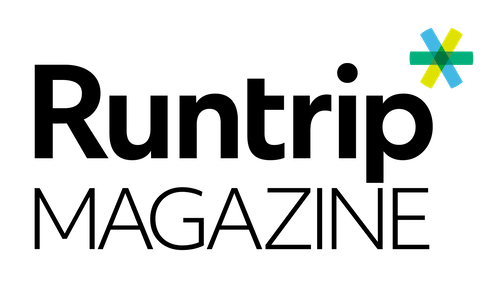日本のスポーツが「我慢・苦労」と離れにくい理由
Sep 27, 2019 / COLUMN
Sep 27, 2019 Updated
この国で、観るスポーツではなく“するスポーツ”といえば? ランナーの方にとっては、まずは走ることが想像できるかと思います。しかし、普段から“するスポーツ”に縁のない方にとって身近なものといえば、例えば『体育』や『部活』の経験を思い出すのではないでしょうか。学校で体育を学びますし、部活動の選択で運動部に入った人もいることでしょう。私たちが学生時代にふれた“するスポーツ”のほとんどが、体育と部活です。
ただ、こと部活においては耳を塞ぎたくなるニュースもしばしば。大阪市立桜宮高校バスケットボール部キャプテンが、顧問からの暴力がもとで自殺した事件は忘れ難いもの。陸上界では、日本体育大学陸上部駅伝ブロック監督だった渡辺正昭氏によるパワハラ騒動がありました。選手も指導者も一生懸命であるがゆえに、望まない結果になることがあるのです。
スポーツはそもそも楽しむもの。ポルトガル語の“deportare”(デポルターレ)という言葉を語源としている『スポーツ』。この言葉は『運び去る、運搬する』を意味しています。つまり、仕事や家事といった日頃の行いから離れる、義務からの気分転換といった要素があります。勝敗や過度の負荷をかけることなく、“楽しみながら”体を動かすことを指しているのです。
ところが、日本ではなかなかどうしてこれが難しい。その理由に一つに、日本のスポーツの始まり方があります。森貴信氏は書籍『スポーツビジネス15兆円時代の到来』で下記のように分析しています。
「日本のスポーツはその管轄が文部科学省だったこともあり、産業というよりも学校教育という側面が強かった。そもそも、明治政府の方針であった『富国強兵』からスタートし、昭和の時代に至るまで、心身ともに健康な兵隊予備軍を作り出すための教育としての『体育』が、日本における『スポーツ』の基礎となってきたのだった」(書籍『スポーツビジネス15兆円時代の到来』より)

現在も、学校の授業でスポーツを行う仕組みは大きく変わることなく続いています。授業としてスポーツに取り組んでいるので、なかなか“楽しむ”という部分を出しにくいのです。これは世界的にみて珍しい光景なのですが、長くこの状態が続いたため、なかなかその違いに気づくことができません。
また、部活においても、基本的には学校の先生が課外活動として取り組んでいます。先生にとっては、詳しくない部活動を担当する場合もあり、自身で学びながら教えている方も少なくありません。当然、先生たちも学校の体育で育ってきた背景があるので、その指導方法に体育のおける指導が踏襲され、どうしても軍隊的な性格が混ざってしまうと森氏は指摘します。もちろん例外もあるかと思いますが、森氏の指摘に頷ける人も多いのでは。
「上の意見には逆らえないなど、内容としては有無を言わせぬような力による指導となってしまうのである。そして、教える側、教えられる側ともに、必然的に『お国のため』から発展した『学校のため』というような、奉仕の精神も求められることになる」(書籍『スポーツビジネス15兆円時代の到来』より)
こういった歴史的な背景が、日本スポーツを“楽しむもの”ではなく、“我慢するもの”“苦しむもの”にしてしまったのです。
ただ、ここにきて少し様子が変わりつつあります。
政府策定の日本再興戦略で、『スポーツ産業を我が国の基幹産業へ成長させる』としているのです。日本の歴史の中で、スポーツを戦略の軸におくのはこれまでなかったこと。数値目標も発表されており、スポーツ市場規模は2015年の5.5兆円を10年後の2025年には15兆円の3倍へ。また、2015年のスポーツ実施率(成人が1週間に1回のスポーツを行う)40.4%を2021年には65%になることを目指します。
これは新たに約2000万人のスポーツ愛好家を創出することになる。簡単な数字ではないことがすぐにわかります。政府は、スポーツの重要性を理解しつつもこれまで腰が重かった人や、学生時代にスポーツに没頭していてドロップアウトした人とスポーツの交わりを目指しているところ。そこには、前時代的な“我慢” “苦しい” “きつい”ではなく、それこそ“楽しい”の部分を伝えることが必然となるのです。
これからより身近な存在になってくるであろう“楽しむスポーツ”。スタジアム一つとっても、街づくりの一つとして考えられており、複合的な機能を組み合わせたサステナブルな交流施設として位置付けるようになっています。スポーツ市場規模が5.5兆円(2015年)から、10年後の2025年には15兆円と見込まれていることからも、これからは“楽しむスポーツ”が充実することが期待できるでしょう。